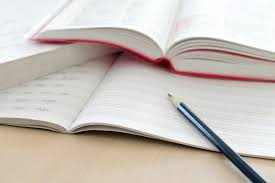
第55話 勉強とサッカー、両立の工夫をスクールコーチが語る!家庭でできる実践術も紹介
✅ はじめに:サッカーと勉強、どちらも大切にしたいあなた
「サッカーが忙しくて、勉強が疎かに…」「勉強ばかりで、サッカーに集中できない…」
そんな悩みを持つ保護者や選手に向けて、ジュニア世代のスクールコーチが実践している“両立の工夫”を紹介します。
実は、勉強とサッカーをうまく両立している子には、ある共通点があります。それは「習慣化」と「メリハリ」。
この記事では、そのポイントをわかりやすく解説し、ご家庭でもすぐに取り入れられる実践方法も紹介!
🎯 この記事でわかること
-
勉強とサッカー、両立できる子の共通点
-
家庭でできる時間管理と声かけの工夫
-
スクールコーチが実践するサポート方法
-
よくある失敗とその対処法
-
今日から始められる具体的な習慣づくり
📘 両立できる子の共通点とは?
まず結論から言うと、「どちらかに偏らない習慣」を持っている子が強いです。
特別に勉強が得意なわけでも、サッカーだけしているわけでもない。けれど、日々の中で上手に「切り替え」できているのです。
① 決まったスケジュールがある
勉強とサッカーを両立している子どもに共通するのが「決まったスケジュール」を持っていることです。何時に練習があり、何時から勉強を始めるのかが習慣化されていることで、迷いやダラダラが減り、集中力が高まります。「帰宅→休憩→勉強→夕食→自主練習」といった流れが自然にできると、毎日の生活にリズムが生まれ、両立が無理なく続けられるようになります。親子で一緒に「毎日の型」を作ることが第一歩です。迷う時間が少ないのもポイント。
② 親のサポートが“管理”でなく“応援”
ポジティブな声かけが、意欲を生みます。勉強やサッカーの両立には、親のサポートが欠かせませんが、大切なのは「管理」ではなく「応援」の姿勢です。「宿題やったの?」と監視するのではなく、「今日もよく頑張ってるね」と認める声かけが、子どもの自信と意欲を育てます。親が味方でいてくれる安心感があると、自ら動こうとする力が湧いてきます。成果を求めるより、努力や継続を温かく見守ることが、両立成功の大きな支えになります。
🧠 両立に必要なマインドセット
両立を語る上で、「やらされている感」からの脱却が大きなカギになります。
✅ サッカーは夢を叶える力に、勉強は夢を広げる力に
サッカーは努力や挑戦を通じて「夢を叶える力」を育てます。一方で、勉強は知識や考える力を広げ、将来の選択肢を増やす「夢を広げる力」となります。どちらも子どもの人生において重要であり、片方を犠牲にするのではなく、互いに補い合う存在として捉えることが大切です。サッカーと勉強、両方に取り組むことで、心と頭のバランスが整い、将来の可能性はより豊かに広がっていきます。勉強は選択肢を広げるツール、サッカーは自分を信じる力を育てる場。
どちらも「将来を形づくる大切な要素」であることを、子ども自身が理解しているかが重要です。
⏰ 家庭でできる時間管理の工夫5選
① タイマーを活用して「集中スイッチ」ON
時間を区切ることで、短時間でも集中できる習慣が身につきます。おすすめは「15分集中→5分休憩」のポモドーロ式。
② 勉強とサッカーの“切り替えリチュアル”を作る
たとえば、サッカーから帰ったらすぐシャワーを浴びて一息→机に向かう、という流れを習慣化。
「何から始めるか」が明確だと、スムーズに勉強に入れます。
③ 朝の10分を活用する
夜は疲れていて集中できない…そんなときは朝にシフト!脳がスッキリしていて、記憶の定着にも効果的です。朝は脳が最もクリアな時間帯。たった10分でも勉強に使うことで、記憶の定着が良くなり、効率的に学習できます。習慣化すれば、毎日の積み重ねが大きな力になります。
④ カレンダーに“可視化”
サッカーや勉強、テストや休息の予定をカレンダーに書き出すことで、時間の流れが明確になり、子ども自身が「今、何をするべきか」を理解しやすくなります。可視化することで先の予定も見通しやすくなり、計画性や自己管理能力が自然と育っていきます。さらに、親子で予定を共有することで、無理のないスケジュール調整ができ、両立へのストレスも軽減されます。まずは1週間単位の簡単な予定表から始めてみましょう。
⑤ 週に1日は「フリーDAY」
サッカーと勉強を両立するうえで、あえて週に1日「何もしない日=フリーDAY」を設けることはとても大切です。心と体を休める時間を意識的に確保することで、他の6日に集中しやすくなり、モチベーションの維持にもつながります。また、自由な時間の中で自分の興味を広げたり、親子でゆっくり会話したりすることで、心のゆとりも生まれます。頑張るためには、リラックスする日も必要。バランスの良い1週間をデザインしましょう。
🗣️ スクールコーチが実践している声かけ術
「サッカーを通して勉強の姿勢も育てたい」
そんな思いで日々指導しています。以下は、実際に使っている声かけ例です。
| シチュエーション | 声かけ例 |
|---|---|
| 練習でうまくいかなかった日 | 「今日の悔しさ、明日の行動に変えよう」 |
| 勉強がはかどらないとき | 「10分だけ一緒にやってみようか?」 |
| どちらも頑張っている時 | 「どっちも大切にしてて、ほんとにすごいね!」 |
❌ よくあるNG例とその対処法
NG①「サッカーより勉強でしょ!」
→ 対処法:両方の価値を肯定する
つい言ってしまいがちな「サッカーより勉強でしょ!」という言葉は、子どものやる気を下げてしまう原因になります。サッカーは子どもにとって大切な自己表現の場であり、努力しているものを否定されると勉強への意欲も失われがちです。大切なのは、どちらにも価値があることを伝えること。「サッカーも大事。勉強も応援してるよ」と両方を認めることで、子どものバランス感覚と自己肯定感が育っていきます。サッカーを否定すると、子どもは勉強にも前向きになれません。
NG②「時間がないなら、サッカーを減らすしかない」
→ 対処法:時間の使い方を一緒に見直す
「時間がないなら、サッカーを減らすしかない」と言ってしまう前に、本当に時間の使い方を見直したかを考えてみましょう。時間が足りないのは“量”ではなく“使い方”に問題があることが多いです。勉強とサッカーは対立するものではなく、工夫次第で両立可能です。優先順位を整理し、スキマ時間を有効活用することで、どちらも継続できます。サッカーを削る前に、「時間を整える」工夫を親子で見つけましょう。「削る」ではなく「整える」ことで、自己管理力も身につきます。
NG③「疲れてるから仕方ないよね」
→ 対処法:疲れてても“少しだけやる”習慣
「疲れてるから仕方ないよね」と毎回受け入れてしまうと、少しの疲れで何も手につかない習慣がついてしまいます。もちろん休息は大切ですが、疲れていても“少しだけやる”意識を持つことで継続力が育ちます。「今日は5分だけ復習しよう」など、小さな一歩を踏み出す習慣が、やがて大きな成果につながります。疲れているときこそ、やり切る体験を積ませることが、子どもの自信と強さを育てていきます。ゼロか100で考えず、1でも進む気持ちを育てましょう。
🛠️ 今日からできる実践習慣5つ
| 実践例 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 1日10分の「おさらいタイム」 | サッカー後に今日の授業内容を軽くチェック |
| ✅ 毎朝、目標を口にする | 「今日は〇〇に集中する!」と宣言する |
| ✅ 家族で1週間の予定共有 | サッカーの試合やテスト前の計画を話す |
| ✅ ごほうび制度を導入 | 両立がうまくできた週は、好きなアイスなど小さなご褒美を |
| ✅ 「できたこと日記」をつける | 小さな成功体験を記録し、自信を育てる |
📈 両立がもたらす“未来力”
サッカーで培われる「集中力」「忍耐力」「協調性」は、勉強や将来の社会生活にも直結します。
逆に、勉強を通じて得られる「計画力」「理解力」「表現力」も、サッカーの戦術理解やコミュニケーションに役立ちます。
つまり、両立は“相乗効果”を生むのです。
🔚 まとめ:両立は難しくない、工夫と声かけで変わる!
勉強とサッカーの両立は、特別な才能や時間がなくても、日々の工夫と親の応援の声かけで大きく変わります。決まったスケジュール作りや時間の「視える化」、そしてポジティブな声かけが子どものやる気を引き出します。完璧を求めず、小さな成功体験を積み重ねることで、自信と継続力が育ちます。両立は難しくない。今日からできるサポートで、子どもの未来を応援しましょう。「勉強とサッカー、どちらも大事にしたい」
そんなお子さんとご家庭のために、“管理する”から“応援する”へとシフトすることが大切です。
今日からできる工夫は、小さなことばかり。でも、その積み重ねが子どもの自信と自立を育てていきます。
💡あわせて読みたいオススメ記事
お問い合わせ
ご質問やご意見、提案、サポートが必要な場合など、どんな内容でもお気軽にお知らせください。また、無料体験も行っております。サッカーを楽しんでいただくための絶好の機会です!チームの雰囲気や練習内容を実際にぜひご体験ください!

